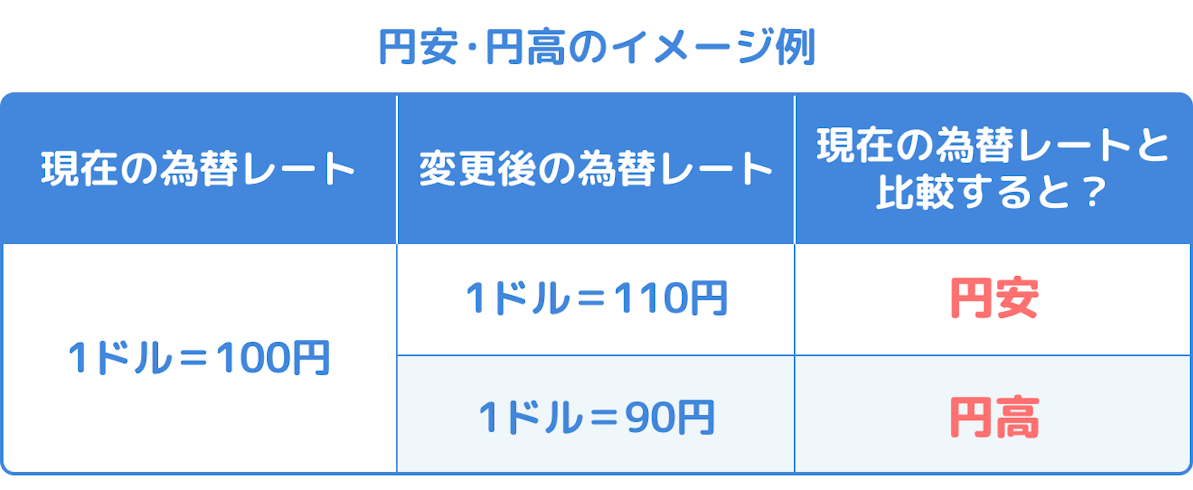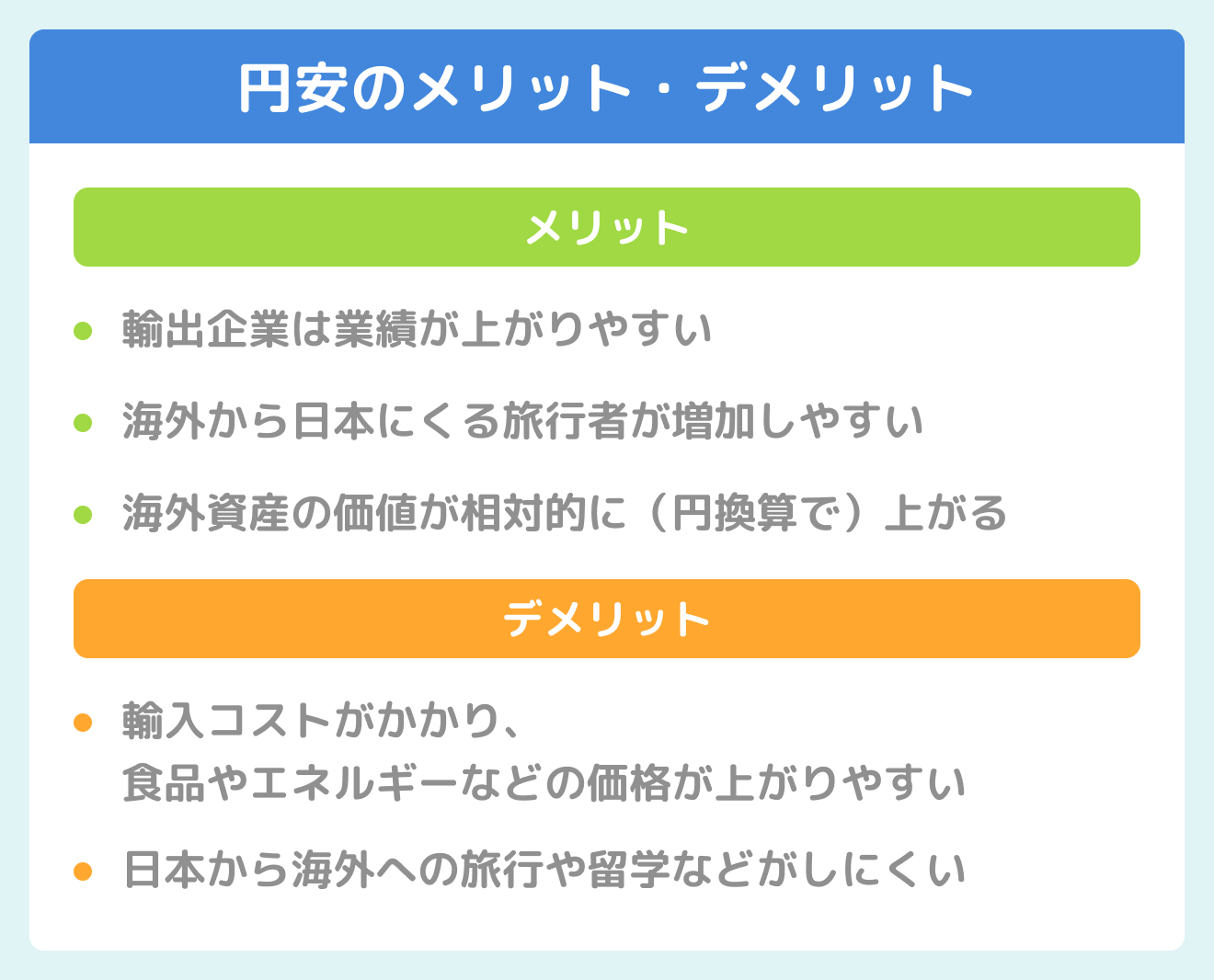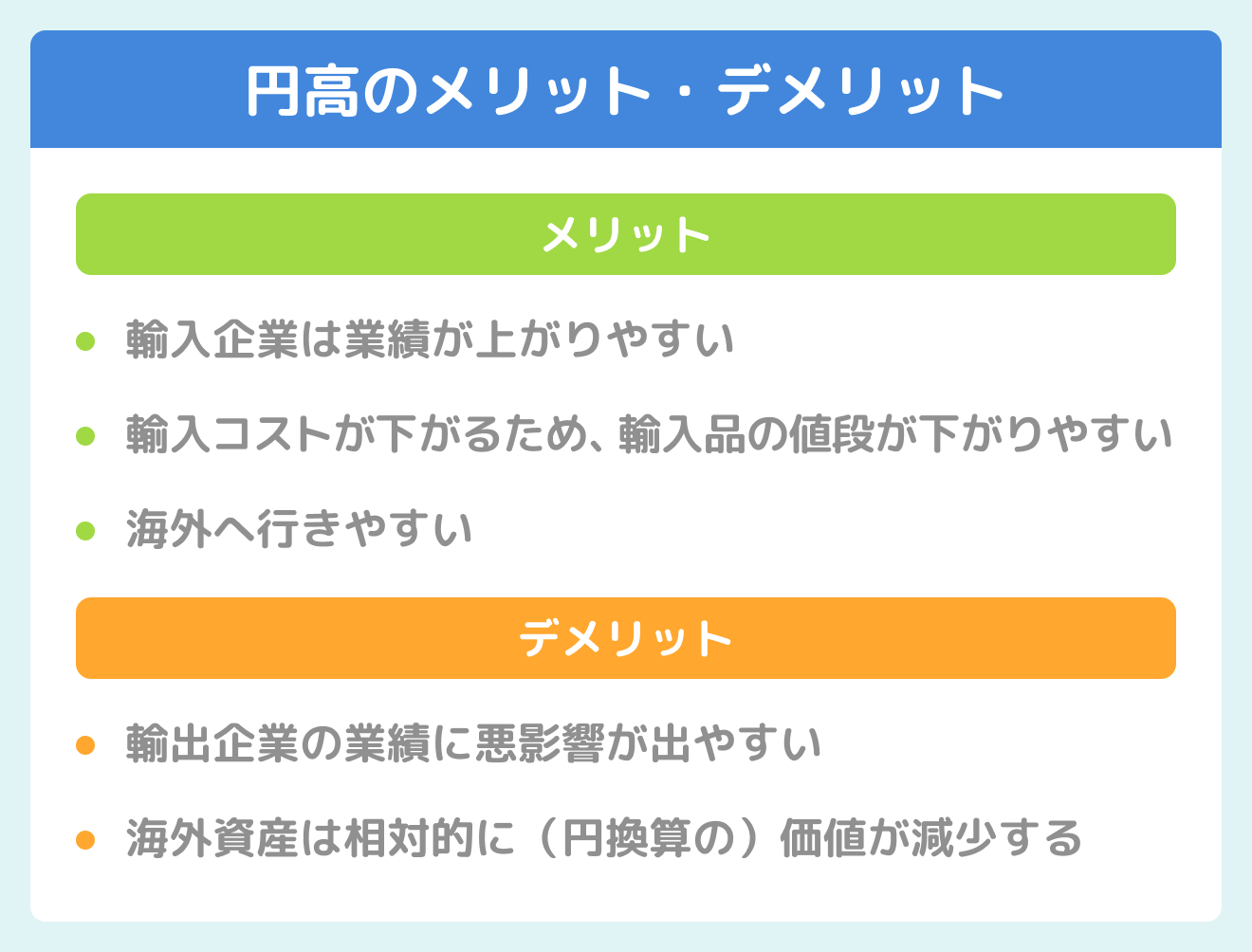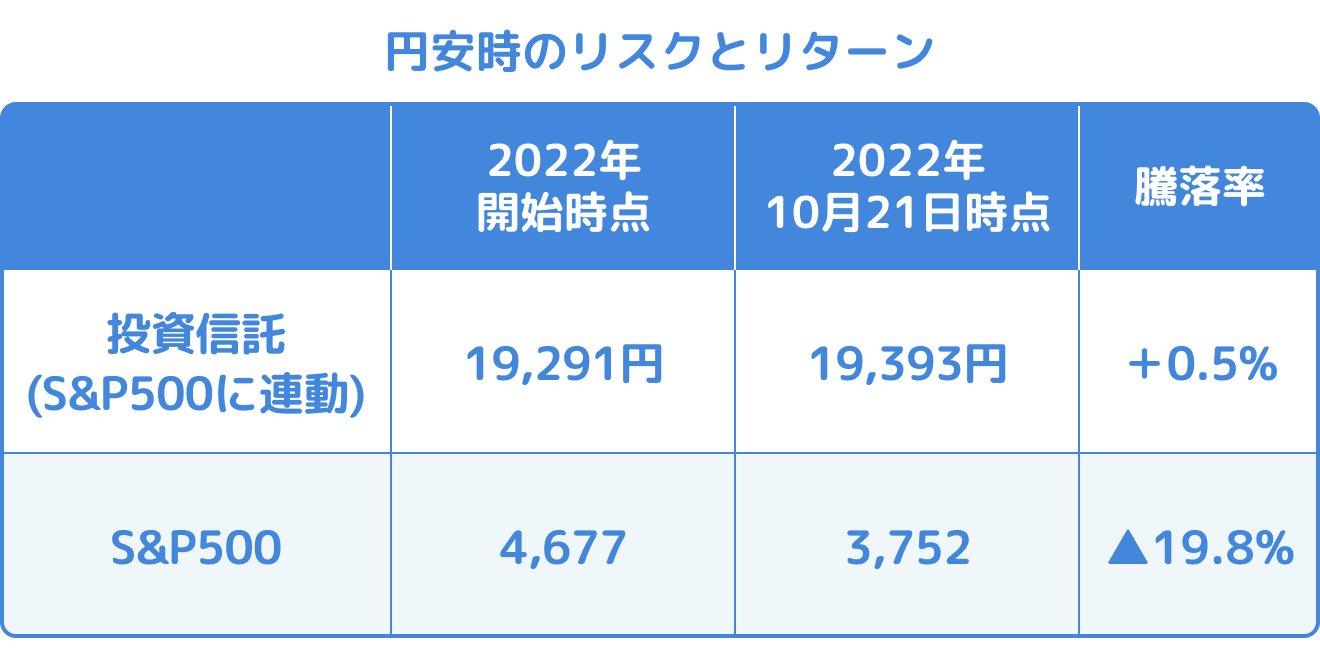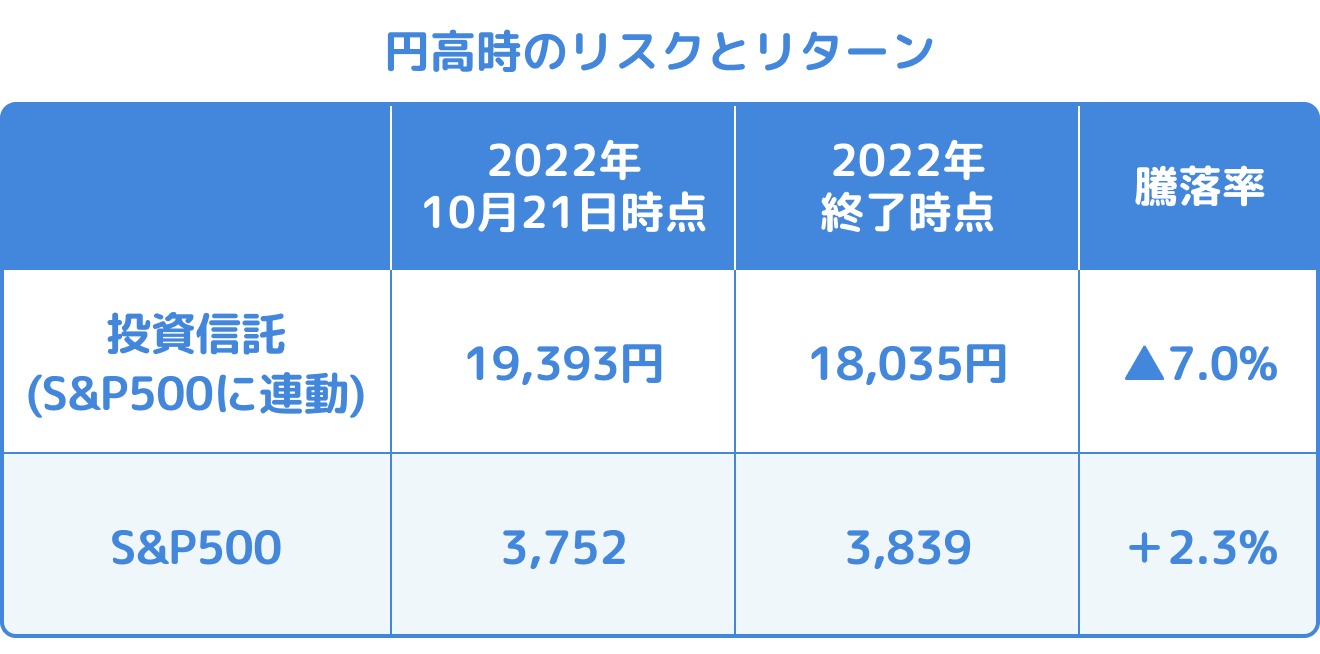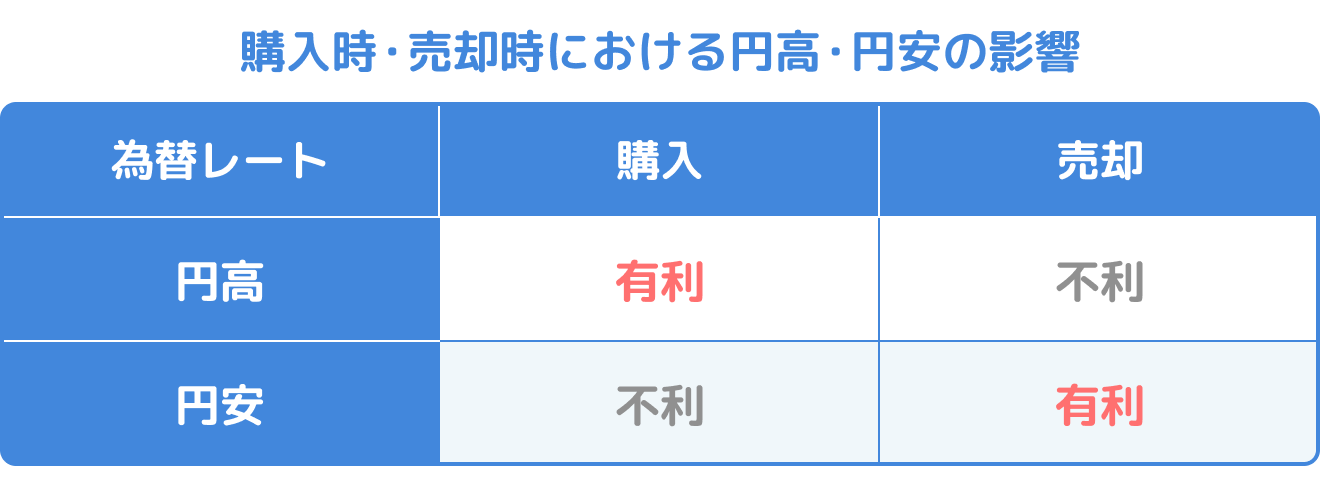1
この「セゾンポケット・金融商品仲介に関する規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が提供するサービスで、次条第1項に定める本サービス(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めています。
2
第3条に定義する利用者(以下「利用者」といいます)になろうとする方には、本規約が本サービスの提供及び利用に関する契約条件として適用されることに同意いただきます。本規約をご確認いただき、内容を理解のうえ同意いただいた方のみ、本サービスをご利用いただけます。
3
ご利用になる本サービスの種類や内容の詳細については、当社が本サービスを説明するサイト(URL:
https://www.saison-pocket.com/
以下「本サイト」といいます)に掲載します。本サイトは、本規約と一体となり本規約を構成し、本サービスの提供及び利用に適用されます。本サイトについてもよくお読みいただき、それらについてもご確認のうえ本サービスをご利用ください。
1
当社は、利用者に対し、本サービスとして、以下各号のサービスを提供します。
(1)利用者が、株式会社スマートプラス(以下「スマートプラス社」といいます)において証券口座を開設(以下「証券口座開設」といいます)することを希望する場合、当該利用者による証券口座開設の申し込みを取次ぐこと(本サービスにより開設された証券口座を以下「本証券口座」といいます)。
(2)利用者に対し、有価証券の売買等の媒介行為を行うこと。
(3)その他本規約に定めること。
(4)上記各号に付帯関連することその他本サービスの管理・運営に必要と当社が判断すること。
2
当社は、委託金融商品取引業者であるスマートプラス社から委託を受け、金融商品仲介業者としての業務を履行します。利用者は、本サービスを通じて証券口座開設をすることで、本証券口座による金融商品取引(以下「金融商品取引」といいます)を行うことができます。利用者(本サービスの申込者を含む。第4項及び第5項において以下同じ)は、証券口座開設及び金融商品取引を自己の責任と判断に基づき行うものとします。
3
本サービスは、インターネット上で提供します。お申込み及びご利用にあたっては、次条第2号に掲げるネットサービス(以下「ネットサービス」といいます)にログインしてください。なお、電話又は店頭での提供はいたしません。
4
利用者は、本サービスの利用にあたり、ネットサービスのID(以下「ネットサービスID」といいます)及びネットサービスのパスワード(以下「ネットサービスPW」といいます)でご利用のネットサービスのものを当社に送信し、ネットサービスにログインしていただきます。なお、当社は、ネットサービス上で本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。その場合は、当該手続きをおとりいただきます。
5
前項において、当社に送信されたネットサービスID及びネットサービスPWと当社の保有する利用者のネットサービスID及びネットサービスPWが一致したとき、及び、前項の手続きを当社が求める場合において、当該手続きをおとりいただいたときは、当社は、利用者が本サービスを利用するものとして取り扱います。
6
当社は、スマートプラス社に所属する金融商品仲介業者として本サービスを提供しますが、利用者が本サービスを利用して行う本証券口座の開設及び有価証券の売買その他の金融商品取引は、利用者とスマートプラス社との間で行うものであり、当社との間で行うものではありません。利用者は、本証券口座及び有価証券の売買その他の金融商品取引についてのお問い合わせ、苦情の申立て等を、金融商品取引業者であるスマートプラス社に対して行うものとします。
本サービスの利用者は、本サービスのお申込みの時点及び利用する期間中、継続して、以下の各号の全てに該当する方ご本人に限ります。
(1)当社発行のセゾンカード又はUCカード(法人カード、コーポレートカードを除きます。以下単に「カード」といいます)のうち、第5号に定義する本件紐付カードとして使用するカードの会員資格を保有する方であること。
なお、セゾンカードについては本会員、UCカードについては本人会員に限ります(本号に該当する方を以下「カード会員」といいます)。家族会員は本サービスをご利用いただけません。
(2)カード会員に当社が提供するネットサービス「Netアンサー」又は「アットユーネット」の会員資格を保有する方(それらの方を以下「ネット会員」といいます)であること。
(3)当社が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認をした方であること。
(4)満18歳以上の方であること
(5)本証券口座の開設にあたり、前条第3項から第5項までの規定に基づき利用者がネットサービスにログインするにあたり使用するネットサービスIDに関連付けられたカード(以下「本件紐付カード」といいます)のご利用代金の支払口座として当該本件紐付カードの会員が指定し当社が認めた金融機関口座(以下「カード届出口座」といいます)の名義人が、当該本件紐付カードの会員本人の名義と同一であること。
1
利用者が本サービスを利用してスマートプラス社において開設する本証券口座は、同社が本サービス利用者向けに同社に開設する本サービス専用の証券口座です。
2
本証券口座の開設は、スマートプラス社所定の条件を満たす方に限らせていただきます。
1
証券口座開設後の、株式売買等の金融商品取引は、全てスマートプラス社への注文、同社との取引となります。当社は、証券口座開設の取次ぎを行いますが、金融商品取引の注文は、直接スマートプラス社宛お願いいたします。
2
金融商品取引の諸条件については、後記スマートプラス社サービスセンターにお問い合わせください。
1
証券口座開設をした利用者が、スマートプラス社との間で投資信託受益権及び株式の累積投資に関する契約を締結している場合において、スマートプラス社の「累積投資約款」、「クレジットカード決済約款」その他の当該契約に関連する約款(それらを総称して以下単に「累積投資約款」といいます)に基づき、当該累積投資取引(以下「対象金融商品取引」といいます)に必要な金銭をスマートプラス社に払い込む(以下「本件払込」といいます)ことを希望するときは、利用者は、本件払込のため、本件紐付カードにかかる当社制定の規約(セゾンカード規約又はUCカード規約。当該規約に付帯関連する特約を含み、以下単に「カード規約」といいます)及び累積投資約款に基づき、本件紐付カードのショッピング機能を利用して、当社をしてスマートプラス社に立替払いさせること(以下「本カード決済サービス」といいます)ができるものとします。
2
カード規約に基づく利用者の商品購入代金の支払方法につき利用者が別途指定した内容にかかわらず、本カード決済サービスのご利用分にかかる当社への支払いは、全て1回払いのみとします。また、本カード決済サービスのご利用分についての支払回数の変更は一切できません。
3
本カード決済サービスで資金を差し入れたことにより行う株式又は投資信託の買付けの時期、買付金額等の諸条件については、累積投資約款の定めるところによります。
4
本カード決済サービスの利用は、当社が永久不滅ポイント規約(以下「ポイント規約」といいます)に基づき付与する永久不滅ポイント(以下「本ポイント」といいます)で、毎月10日までに当社へ到着したショッピングご利用合計金額に対し、1,000円につき1ポイント(以下「ショッピングポイント」といいます)を付与するサービスの対象外です(本件紐付カードが第三者との提携カードである場合における、提携先ポイントサービスについても同様に付与対象外となります)。なお、本カード決済サービスの利用にあたって本ポイントを付与する場合の条件については、本サイトに掲示していますのでそちらをご確認ください。
5
利用者は、クレジットカードのショッピング枠の現金化を目的とした本カード決済サービスの利用をしないものとします。
6
当社が、利用者が前項の規定に違反したと合理的に判断した場合には、利用者による本サービス又は本カード決済サービスの利用を終了させることができるほか、カードの会員資格の喪失等の処置をとる場合があります。
1
利用者は、永久不滅ポイント規約(URL:https://www.saisoncard.co.jp/point/pdf/aqf_kiyaku.pdf?20200331 以下「ポイント規約」といいます)の定めにかかわらず、本証券口座による対象金融商品取引又はスマートプラス社が認める取引に必要な金銭の全部又は一部に充当する目的に限り、当社に対し、利用者が有する永久不滅ポイントを当社が別途定める換算レート及び買取単位にて買い取ることを請求すること、及び、当該買取代金相当額を本証券口座による対象金融商品取引又はスマートプラス社が認める取引に必要な金銭の全部又は一部に充当すること(当社がスマートプラスから当該金銭の収納代行の委託を受けて代理受領することを含みます)を請求することができるものとします(以下当該請求に応じて当社が提供するサービスを「本ポイント決済サービス」といいます)。
2
当社は、利用者が本ポイント決済サービスの利用を当社所定の方法により申し出た場合において、当該申し出を受けた時点で、利用者がポイント規約に基づき永久不滅ポイントを利用することを請求できる資格を有するときは、当該申し出を承諾し、利用者に本ポイント決済サービスを提供します。
3
本ポイント決済サービスは、第3条各号の全てに該当する方であることに加えて、本件紐付カードのうち、本カード決済サービスを除くショッピングサービスの利用によりショッピングポイントの付与対象であるカードの会員資格を保有する方のみが利用可能なサービスです。
4
本ポイント決済サービスで資金を差し入れたことにより行う投資信託の買付けの時期、買付金額等の諸条件については、本証券口座にかかるスマートプラス社の証券取引約款の定めるところによります。
5
利用者が、本ポイント決済サービスの申し出をして、当社が撤回を受け入れた場合またはその他当社所定の場合において、撤回した時点で当社が既にポイント数を減算しているときの当該減算ポイント数の利用者に対する返戻は、当社所定の時期、方法によります。
1
本サービスの利用料金は、無料です。但し、通信料金は利用者にご負担いただきます。通信料金については、利用する通信サービス事業者との契約をご確認ください。
2
利用者は、自己の責任と負担において、本サービスの利用に必要な環境(ネットサービスの利用のための端末機器等並びに電話利用契約及びインターネット接続契約等を含むがそれらに限られません)を維持するものとします。
3
利用者とスマートプラス社との間の取引に際しては、別途同社への手数料の支払いが必要な場合がございます。
本サービスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、当社、スマートプラス社その他権利を有する第三者に帰属します。
利用者は、次に掲げる事項のいずれもしてはならないものとします。
(1)第三者に本サービスを使用させること、又はネットサービスIDもしくはネットサービスPWを不正に使用すること
(2)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置くこと
(3)通常の利用の範囲を超えて、当社又はスマートプラス社のシステムもしくはネットワーク又はそれらに接続されるシステムもしくはネットワークに過度な負担をかけもしくはそれを助長すること、その他当社の業務運営・サービス提供を妨害し、又はそれらに支障をきたすこと
(4)当社、スマートプラス社もしくは第三者に不利益を与え、又はこれらの営業を妨害すること(当社のシステム又はウェブサイト等に対する不正アクセス、有害なプログラムを送信することを含みます)
(5)本サービスを第三者に対し有償、無償問わず、配布、再使用許諾その他の方法で使用させ、又は再許諾権の設定もしくは担保に供する行為をすること
(6)上記のほか、当社又はスマートプラス社の知的財産権を含む法的権利を侵害する行為又はそれらのおそれのある行為をすること
(7)本サービスを利用する地位又は権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸、質入れ、担保設定その他の処分をすること
(8)上記各号のほか、金融商品取引法その他関連法令等もしくは本規約に違反すること、又は公序良俗に反することもしくはそれらのおそれのあること
(9)その他本サービス又は本サービスの運営において当社が不適当と合理的に判断し、かつ、当社が禁止する旨を利用者に通知し又は公表したこと
利用者は、本サービス又はネットサービス等の保守、更新等のため、当社が本サービスの全部又は一部を停止することがあることを予め異議なく承諾します。なお、緊急時の停止を除き、当社は、本サービスの停止につき、事前に当社所定の方法によりお知らせします。
当社は、天災、労働紛争、停電、通信インフラの障害、公共サービスの停止、自然現象、暴動、政府の行為、テロ、戦争その他の不可抗力により利用者に生じた損害について、一切責任を負いません。
1
本サービスは、原則として本証券口座にかかる利用者とスマートプラス社との間の契約が有効である期間中、有効に存続します。
2
本サービスの利用の終了をご希望の場合は、前項の契約を終了していただくものとします。
利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、利用者に事前に催告又は通知することなく、利用者による本サービスの利用の全部又は一部を終了もしくは停止させ、又はネットサービスの会員資格を喪失させることのいずれか又は両方を行うことができるものとします。
(1)ネットサービスの規約又は本規約の一つにでも違反した場合
(2)本件紐付カードの会員資格もしくはネットサービスの会員資格の喪失事由のいずれかに該当した場合、又はそれらの資格のいずれかを喪失した場合
(3)第3条各号の条件のいずれかを充足しなくなった場合、又は充足していなかったことが判明した場合
(4)利用者とスマートプラス社との間の本証券口座に関する契約又はそれに付帯関連する契約が終了した場合
(5)利用者による本サービスの利用が適当でないと当社が合理的に判断した場合
(6)事実に反する情報の申告又は登録があった場合
本サービスに関する利用者と当社との契約が終了した場合においても、第2条第5項及び第6項、第5条第2項、第6条第2項から第4項まで、第7条第4項及び第5項、第8条、第9条、第12条、本条、次条、並びに第19条以降の規定は当該終了後も引き続き効力を有するものとします。
1
本サービスの利用に関して利用者がスマートプラス社又は第三者に損害を与えた場合、利用者は、自らの責任と負担においてそれを解決し、当社に損害を与えないものとします。
2
利用者による本規約の違反又は違法行為によって当社に損害を与えた場合、当社は、利用者に対して賠償を請求することができます。
3
本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、ネットサービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。
1
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を本サイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で利用者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(2)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ本サイトへの掲載等を行うものとします。
(1)変更の内容が利用者の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2
当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を本サイトにおいて告知する方法又は利用者に通知する方法その他当社所定の方法により利用者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本利用者は、当該周知の後に利用者が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
1 本規約の準拠法は、日本法とします。
2 本規約及び本サービスに関連して利用者と当社との間で訴訟、調停その他の紛争解決手続の必要が生じた場合は、訴額の多少にかかわらず、利用者の住所地及び当社の本社、支社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約に定めのない事項については、カード規約(個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項その他関連する諸規定を含みます)、ネットサービスの規約、ポイント規約及び「セゾンポケット・金融商品仲介に関する規約
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」の定めるところによります。
以上
附則
2019年11月12日制定
2025年2月28日制定
(問い合わせ先)
本サービスに関するお問い合わせ及びご意見の申し出等につきましては、下記の当社窓口までお願いいたします。
■セゾンカード会員の方
カスタマーサポート https://www.saisoncard.co.jp/customer-support/
■UCカード会員の方
カスタマーサポート https://www2.uccard.co.jp/cs/customer-support/
(スマートプラス社問い合わせ先)
スマートプラス・セゾンポケット窓口
電話番号 050-1746-2847(月~金 8:30~17:30 祝日、年末年始休)
メールアドレス support-saison.pocket@smartplus-sec.com